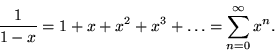
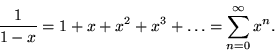
10 'First few terms of Taylor expansion
100 '*** graphic initialization
120 cls
130 screen 1:console 0,25,0
140 x1=-1.5:x2= 2.0:'<-- range of X ( X1 < X2 )
150 y1=-1.0:y2= 10.0:'<-- range of Y ( Y1 < Y2 )
160 window (x1,y2)-(x2,y1)
170 line (x1,0)-(x2,0),7:'<-- x-axis
180 line (0,y1)-(0,y2),7:'<-- y-axis
200 '*** plotting
210 n=640
220 dx=(x2-x1)/n
230 input "m=";m
510 pset (x1,fnF(x1,m)),1
520 for i=1 to n
530 x=x1+i*dx
540 line -(x,fnF(x,m)),1
550 next
999 end
1000 *** definition of function
1005 fnF(x,m)
1010 local n,s
1020 s=0.0
1030 for n=0 to m
1040 s=s+x^n
1050 next
1060 return(s)
230行目の input は,プログラム実行時に変数に値を代入したいとき
に使う.プログラムを書いたら適当な名前で保存しておこう.それから
run してみよう (m の値をだんだん増やしていくとどうなるか観
察しよう).
510行目では第一引数を x1 として関数を呼んでいる. また変数 n はメインプログラム中でも使われている (210行目) し, 関数定義の中でも使われている (1030行目).しかし関数定義中の n は local 変数なのでメインプログラム中の n とは関係ない (影響を及ぼ さない) のだ.
なお,このプログラムの最初の部分 (100〜180行) は, グラフィックを利用するときにいつでも使えるので,この部分だけファイルに 保存しておくと便利だ (いつでも再利用できるように).